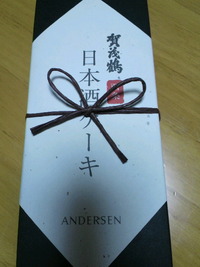2008年12月20日
室礼講座
本日は松風園で行われた室礼(しつらい)講座「正月編」に参加してきました。
「しつらい」とは、季節のものに思いをたくし、祈ること――。
(室礼三千HPより)
講師は室礼三千専任講師の宮田由美子先生。
日本文化の基本から、お正月飾りまでほんとにたくさんのことを学びました。
門松や鏡餅、お年玉の意味など存じませんでした・・・。
ひとつひとつの意味を学び、実際に鏡餅を飾りました。
地方によって飾るものは違いますが、本日は室礼三千の飾り方です。
餅を大小重ねるのは、福徳の重なることを願う心・・・。

左上から右回りに
■コロ柿
カラスも食べない渋柿が修練の後には床上の飾りにまでなりえるという精神の気高さを表現。
ヘタがついているのは、代々繋がるように・・・
■田作り(ごまめ)
豊穣や子孫繁栄を願います。
おせち料理の場合は(頭の)方向を揃えますが、飾りのときは「八方に広がるように」とあえてバラバラの方向に。
■勝ち栗
「勝ち」を願います。
また、栗はあのイガイガの中に3つ1組で入っています。
真ん中は平べったく、両サイドは反面が丸くなっていますが、その形が仏様の形に似ているということも理由のひとつです。
■黒豆
「豆豆しく達者で」健康を願います。
どこから飾ってもOKですが、祝い事ですから右回りに飾っていきます。
ちなみに死者を迎える盆踊りは左回り・・・。
「お年玉」は、もともと神に備えた鏡餅のお下がり=年神様の魂のお下がり。
鏡餅時代が「お年玉」。
江戸時代、商人の方々が奉公人に現金を渡すようになり、それが現在のお年玉の形になったそうです。
というわけで、鏡餅のところにお年玉袋を飾り、それを子どもたちに渡しながら由来を説明されては?というお話もありました。

餅花の作り方も習いました。
今年は喪中ですから、来年末に挑戦してみます。
晩白柚を鈴に見立てた飾り。

柑橘の「橘」=吉ということで、中でも大きな晩白柚は大吉!!
お正月の贈り物によいそうです。
年始挨拶の手土産に購入しようと思います。
「おめでとう」と由来は「新芽が出る」
というわけで、新芽が出ている野菜を飾るのもよいそうです。

全てのことには意味があるのですね。
その意味を知ってやると、だた「決まりだから」とやるのでは、気持ちの入り方が違うような気がいたします。
参加してほんとによかった♪
「しつらい」とは、季節のものに思いをたくし、祈ること――。
(室礼三千HPより)
講師は室礼三千専任講師の宮田由美子先生。
日本文化の基本から、お正月飾りまでほんとにたくさんのことを学びました。
門松や鏡餅、お年玉の意味など存じませんでした・・・。
ひとつひとつの意味を学び、実際に鏡餅を飾りました。
地方によって飾るものは違いますが、本日は室礼三千の飾り方です。
餅を大小重ねるのは、福徳の重なることを願う心・・・。
左上から右回りに
■コロ柿
カラスも食べない渋柿が修練の後には床上の飾りにまでなりえるという精神の気高さを表現。
ヘタがついているのは、代々繋がるように・・・
■田作り(ごまめ)
豊穣や子孫繁栄を願います。
おせち料理の場合は(頭の)方向を揃えますが、飾りのときは「八方に広がるように」とあえてバラバラの方向に。
■勝ち栗
「勝ち」を願います。
また、栗はあのイガイガの中に3つ1組で入っています。
真ん中は平べったく、両サイドは反面が丸くなっていますが、その形が仏様の形に似ているということも理由のひとつです。
■黒豆
「豆豆しく達者で」健康を願います。
どこから飾ってもOKですが、祝い事ですから右回りに飾っていきます。
ちなみに死者を迎える盆踊りは左回り・・・。
「お年玉」は、もともと神に備えた鏡餅のお下がり=年神様の魂のお下がり。
鏡餅時代が「お年玉」。
江戸時代、商人の方々が奉公人に現金を渡すようになり、それが現在のお年玉の形になったそうです。
というわけで、鏡餅のところにお年玉袋を飾り、それを子どもたちに渡しながら由来を説明されては?というお話もありました。
餅花の作り方も習いました。
今年は喪中ですから、来年末に挑戦してみます。
晩白柚を鈴に見立てた飾り。
柑橘の「橘」=吉ということで、中でも大きな晩白柚は大吉!!
お正月の贈り物によいそうです。
年始挨拶の手土産に購入しようと思います。
「おめでとう」と由来は「新芽が出る」
というわけで、新芽が出ている野菜を飾るのもよいそうです。
全てのことには意味があるのですね。
その意味を知ってやると、だた「決まりだから」とやるのでは、気持ちの入り方が違うような気がいたします。
参加してほんとによかった♪
Posted by tacky at 23:44│Comments(0)
│お菓子